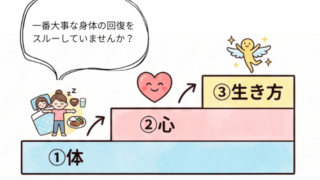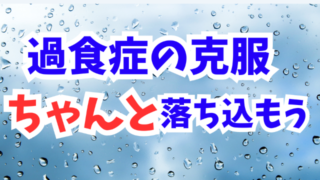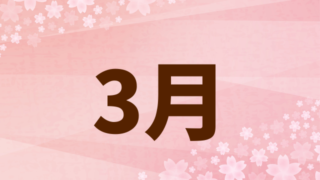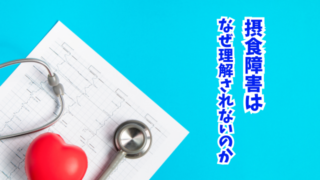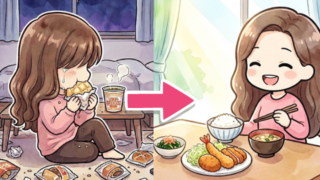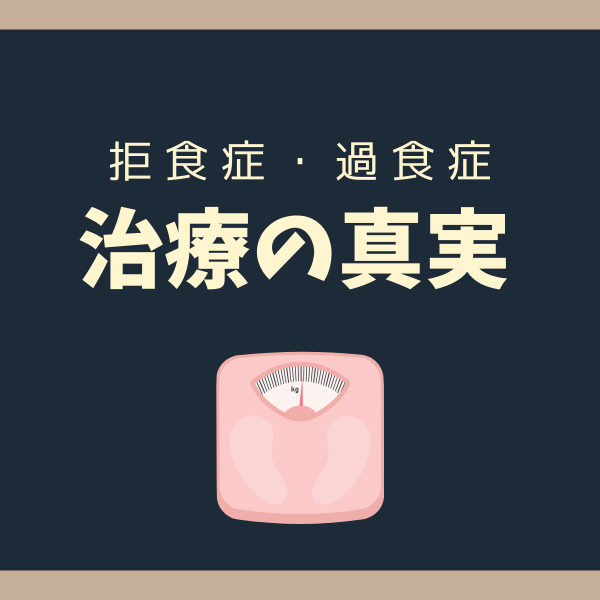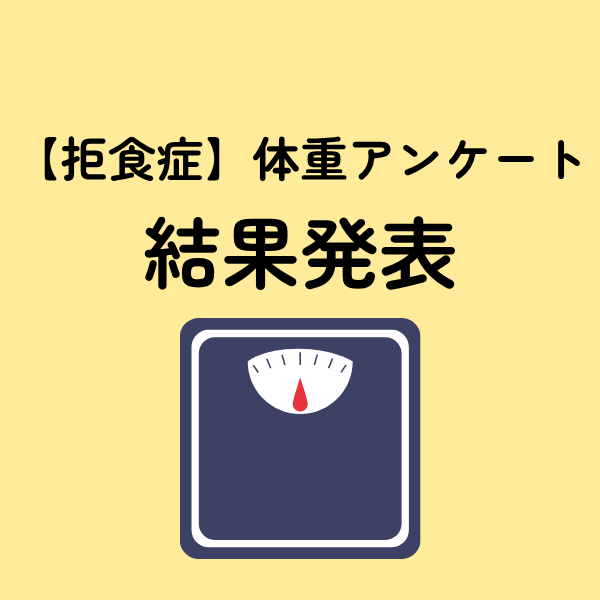摂食障害専門カウンセラー中村綾子です。
拒食症が長引いているお嬢様を見ていると、
「とにかく食べて体重が増えれば、あとは自然とフツーに戻れるのでは…」
と願いたくなるものです。
ですが実際には、【拒食症の世界】と【フツーの世界】は延長線上にあるわけではありません。
【拒食症の世界】と【フツーの世界】は、別々のもので、別世界なのです。
■【拒食症の世界】
お嬢様とお母様、それぞれが「拒食症の世界」にハマってしまっている状況を書き出してみます。
■【拒食症の世界】お嬢様の様子
・ 栄養剤を飲むことが「生活の一部」になっている
・体重の増減に心が振り回される
・ 毎日カロリーを計算してしまう
・「太りたくない」「太るのがこわい」という気持でいっぱい
・些細なことでイライラしがち
・お出かけは友達より、お母様とベッタリ…etc.
■【拒食症の世界】お母様の様子
・お嬢様の食事をキッチリ管理してしまう(カロリー計算、栄養バランス、時間管理…etc.)
・お嬢様の体重が増えないと自分のせい…と落ち込んでしまう
・実際のお嬢様は、低体重にも関わらず、「そんなに痩せていないんじゃない?」と思えてくる
・摂食障害の通院や入院、そして日々の栄養剤の摂取が、日常的になっている
・学校などへの送迎が当たり前に行っている
・病院を調べたり、学校への問い合わせをしたり、率先して行うのがいつもお母様の役割になっている…etc.
■【フツーの世界】
お嬢様とお母様、それぞれが「フツーの世界」にいる場合の言葉や行動を書き出してみました。お嬢様の同級生やそのご家族は、こんな感じでないないでしょうか?
■【フツーの世界】お嬢様の様子
・「太っちゃった~」と笑いながら友達と話せる
・当たり前のように、ほぼ毎日、学校や仕事に通う
・「ケーキ食べに行こう!」など、友人から誘われたら自然に応じられる
・食事のカロリーなんて考えない
・食べても食べなくても、体型がほぼ一定になっている
・病院に行くのは、インフルなどの寝込んだ時だけ
・喜怒哀楽はあるけれど、黙り込んだり、長期間泣いたりすることがほとんどない。
・悩んでも、学校の先生や友人に相談して、自力で解決できることが多い
■【フツーの世界】お母様の様子
・食事の用意はするものの、手抜きも外食も気楽にできる
・お母様自身の趣味が充実してる
・お嬢様の進路は自分で決めるから、基本的にノータッチ
・お嬢様の体重には、ほぼ無関心
・お嬢様が友達付き合いに忙しく、お母様はご夫婦で旅行したり、お友達と出かけたりで忙しい。
・家族間で意見が食い違うことがあっても、話し合いで解決できる…etc.
拒食症:身体の回復と心の回復はちがう

*「もう大丈夫」と思われているからこそ、ツライなんて言えない
多くのお母様が安心してしまう場面は
・入院しなくなった
・3食食べられるようになった
・生理が戻った
といった身体の回復です。
もちろん、それはとても大きな一歩です。
ですが、それだけで拒食症が「治った」とは言えません。
摂食障害からの回復で本当に時間がかかるのは、身体ではなく【心の回復】です。
* 摂食障害の背景にある《原因》と向き合うこと
* 食事や体重から心を解放していくこと
* ほんとうの自分を受け入れていくこと
これらには、身体の回復以上に長い時間が必要です。
身体が整った後に、ようやく「心の回復」に向けて取り組む【次の段階】が始まるのです。
拒食症の心の回復こそ、身体の回復の何倍もの時間がかかるのです。
拒食症からフツーの世界へ:お母様にできること

*どうして、うちの娘は摂食障害になったの…
お嬢様が本当に【フツーの世界】へ戻るためには、まずお母様がこうした「流れ」を理解しておくことが大切です。
・ 「食べられる=治った」ではないこと
・身体の回復の後に、【心の回復】に何倍もの時間を費やす必要があること
・摂食障害の原因を理解すること(参照動画)
私は摂食障害専門カウンセラーとして、数多くのお母様とともに「身体の回復の先にある心の回復」をサポートしてきました。
もし今、「体重が回復したのに、どうして元気にならないの?」と感じていらっしゃるなら、それは【心の回復】に切り替えるタイミングに来ているのかもしれません。
ぜひ一度、摂食障害の専門家とお話ししてみませんか?
▼お母様のための摂食障害専門カウンセリング、詳細はこちら

▼オススメ記事