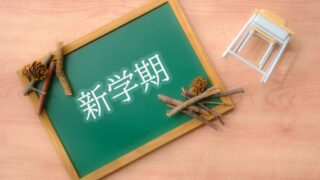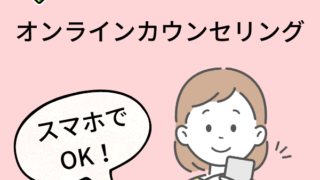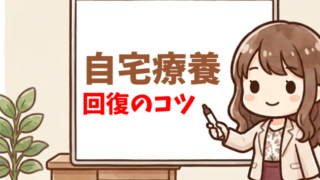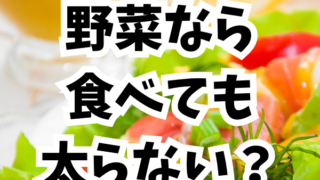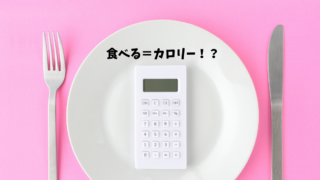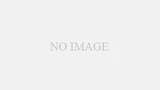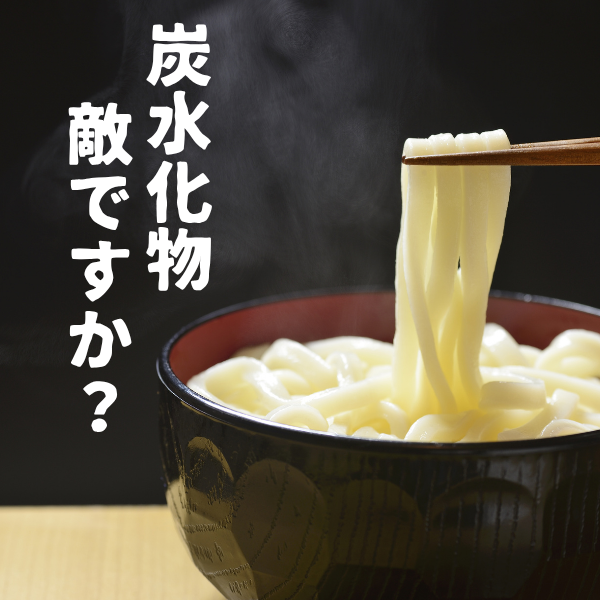摂食障害カウンセリング
中村綾子です。
食べた後の罪悪感。。。
これは、気持ちの上だけではなく、身体がグッタリすることも含まれているかもしれません。
でも、摂食障害が治る過程の中で、少しずつラクになっていくことの1つです。
メルマガ読者様からいただきましたご質問をご紹介します(メルマガのご案内)。
◆メルマガ読者さんからのご質問◆
食後ひどい頭痛や脱力感があるのですが、これも摂食障害の症状なのでしょうか?
*ブログでは、一般論と私の経験談の範囲で回答させていただきます。
ご質問をありがとうございます。
「摂食障害だから、こうした症状が出る」というより、摂食障害によって、身体全体が変わってしまったから、症状が出る、と考えたほうがよさそうです。
順番としては・・
食事量が減る
↓
胃腸が動く量・時間が減る
↓
身体に少しのエネルギーしか入らない
↓
少しのエネルギーで生きていくしかない
↓
体力・血圧・筋力など、全体の身体の機能低下
*これは、医学的見解ではないので症状については主治医のもとで検査などを行ってください*
これらの身体の変化とともに、食に対する「気持ち」の部分も大きいのです。
以下の3つを基にお届けします。
1.消化につかわれるエネルギー
この考えは、知人・薬剤師から聞いた話がもとになっています。
消化につかうエネルギーもある
摂食障害で、体力が低下している中、食べたものを消化するために、さらにエネルギーと使わないといけないんです。
なので、エネルギー不足の中から、エネルギーをひねりだしている状態^^;;
消化する際、血液は胃に集中します。
でも、血液の全体量がすくない中、胃に寄せ集められてしまうのです。
結果・・・頭のほうに血液が充分に回らなくなります。
そのため、頭痛がしたり、クラクラしたりという症状がでます。
脱力感や身体が怠く感じるのも、消化につかうエネルギーによって、他の部分がツラくなるのではないでしょうか?
2.【拒食症あるある】食べることに緊張していませんか?
食べることに緊張していませんか?
食べなきゃいけない!
食べないと入院になる!
でも・・・
太ったらどうしよう?
治ったら、どんな体重になるんだろう?
元気になったら、誰も心配してくれなくなる・・・etc.
1回の食について、本当にさまざまな気持ちが入り混じっているのではないでしょうか?
だから、食に対して完ぺきを求め、食に対して、異様なほど緊張してしまうのです。
自己流よりも
専門家
1人で何もかも背負いこむよりも
「やり方」を身につける
私は心のカウンセリングと共に、食べ方を見直すことも大事だと考えています。
今のあなたは、「食べ方」が分かっていますか?
▼動画で学べる食べ方

3.症状がおさまっていった経験談
私の経験談です。
拒食真っ最中の頃は、食後がものすごくつらかったです。
身体全体が怠くて
胃がどーーんと重く苦しくて
「食べなければよかった」
毎日、毎日、そんな気持ちでいっぱいでした。
その結果・・・入院。
精神科入院ほど、ツラく嫌なものはありませんでした。
後々、多額の入院費を、知りました。
だから、入院以外の方法で、ちゃんと治ろうと思えたのかもしれません。
過食になったことも
転院10回したことも
食後の不調が緩和していく過程と、少しずつ関係しています。
この症状も、「◯月◯日に治りました!」と言えるものではなく、なんとなく、いつの間にか消えていったことの1つです。
ですが・・・
1番大きい変化は、治ることに主体的になったこと
きっと最初の5年くらいは、「治してほしい」「分かってほしい」ばかりだったと思います。
でも・・・
経験者ではない医者が「分かる」こともあり得ないのです。
「治してほしい」と願ったところで、治るのは自分自身なのです。
そう気づきはじめた頃、食後の不調をはじめ、さまざまな症状と症状に対する気持ちが、変化していったように思います。
・・・
治ることは、向き合うこと
向き合うために、客観的な視点を大切にすること
摂食障害のほんとうの原因と向き合うことを、忘れていませんか?