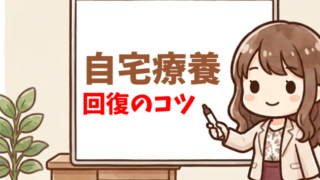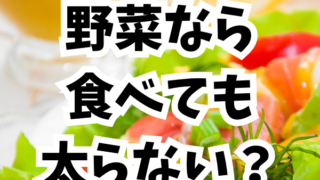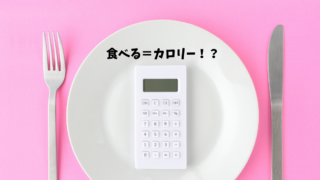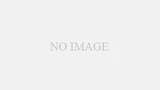摂食障害カウンセリング
中村綾子です。
お菓子を全く食べなくなる人もいるし
逆にお菓子ばかりが「食事」になってしまう人もいるし
「カロリーが同じなら、何食べても一緒でしょ!」
「お菓子が『食べたいもの』なんだから!」
とお菓子中心の生活を正当化してる人もいます^^;;

メルマガ読者さまからいただきましたご質問をご紹介します。
(⇒摂食障害に関するご質問は、こちらのメルマガから受付中です)
*ブログ回答は、私の個人的な経験とカウンセリング方針に基づいています。
*全ての方に当てはまるとは限りませんので、予めご了承ください。
◆メルマガ読者さんからのご質問◆
私は、三食の食事を食べることより、お菓子を食べようとしてしまいます。
30才になって、自分の行動や思考が「異常」だと気付きました。
この異常な思考を一般的にする為には、普段から何を考え、どんなことを優先したらいいのでしょうか。
ご質問をありがとうございます。
考え方・知識・行動の3つに分けて、できるところから取り組んでいくことをオススメします。
1.【知識】お菓子ばかりを食べ続ける弊害
ごくカンタンに言うと、
隠れ肥満になりやすいです。
身体の中の中性脂肪がたまって
見た目フツーでも、実は体脂肪が多い身体だったり
体重は少ないのにお腹ポッコリになる傾向があるようです。
お菓子は「食べたらいけないもの」ではないけれど、
お菓子だけでは、身体の中にいい循環が起こらないのではないでしょうか?
食べて
食べたものをエネルギーに変えていくには
ビタミン類をはじめとする色んな栄養素が必要なんです。
カロリー摂取だけでは、
身体がラクに動くためには
足りないものもいっぱいあるんです^^
2.【行動】一人分の食事量を知る時間
摂食障害に悩んでいる方の多くは、
コレにも悩んでいます。
「1人分の食事量が分からない」
分からないから
いつもいつも食べ過ぎなんじゃないか?と不安になったり
分からないから
控えて控えて食べてしまったり
分からないから、
「あの人のほうが多い!」と気になって仕方がなかったり
だから、行動してほしいのです。
1人分の食事量を体験するための行動です。
それは、外食して定食を注文すること。

*仕事帰りの夕飯風景。外食しても、私はいつも完食です。
家の食事だと、長年染みついた自己流になっている場合が多いので、「治療費」としてひとりで外食をしてみることをオススメします。
まずランチを食べに一回行ってみて、「多い」と感じたらまた違うお店で定食を頼んでみたらいいのです。
それが世の中の1人分だから。
知ることで、「分かる」につながるかどうか、分かりません。
なんど、定食を頼んでも「分かった」と思えないのなら、それは、知識の問題ではないことがわかってくるはずです。
知識として
栄養学として
「知って」いても
あなたの心が納得していないから、
いつまでたっても「1人分が分かりません」という言葉に
なるのではないでしょうか?
3.【気持ち】普通になりたいけれど、普通が怖い
「1人分の食事量が分かりません」という言葉には、
様々な気持ちが隠されているように思います。
一人前の社会人として扱われる恐怖
普通の人に戻る不安
普通になりたくてたまらないのに
普通に戻るのが怖い
ちゃんと働いて認められたいのに
働くこと・社会に出ることが怖い
普通に食べちゃったら
普通の身体になってしまう
普通の身体になってしまったら
何もかもちゃんとやらないといけない・・・etc.
そんな気持ちに気付いているでしょうか?
今の恐怖が、いつの間にか1人分の食事を避け、避け続けている間に「分からない」という言葉に置き換わっていることに気づいているでしょうか?
私は、「怖い」なら、「怖い」と言ってもいいと思います。
ブランクの後に、社会に出ることは怖くて当然です。
職場で上手くいかなかった経験を持つなら、怖いと感じることが当たり前なのです。
でも、社会復帰について、あなたが自分の気持ちに正直になって、素直に言葉に表していくことが、必要なのではないでしょうか?
▼自分のメンタルを大切にしながら仕事がしたい方はこちら

▼ 進学・就職に悩む学生さん(&保護者)の場合は、こちら